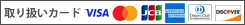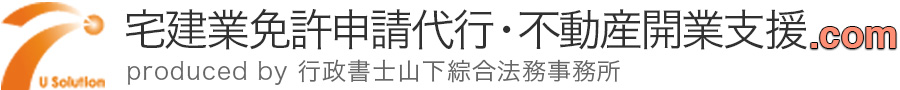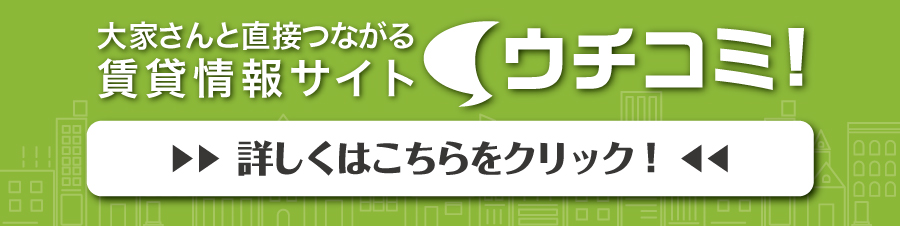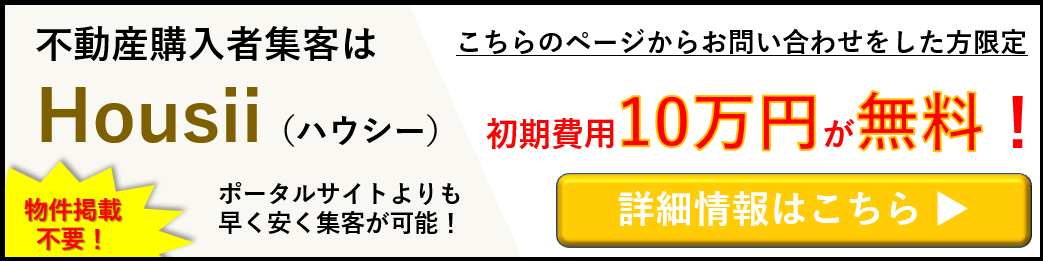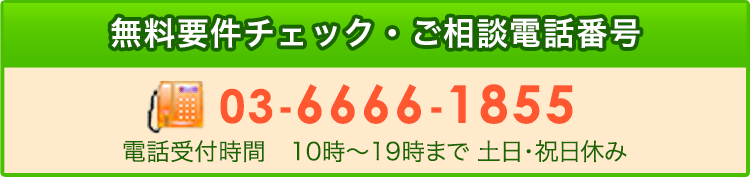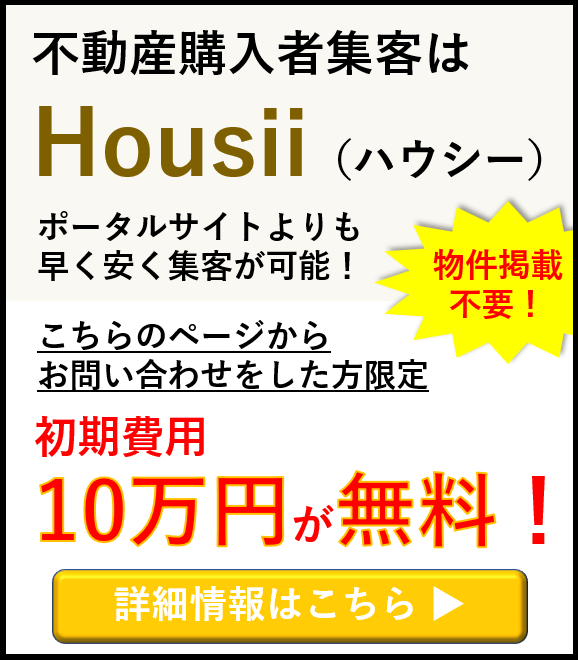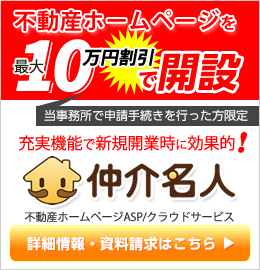個人免許から法人免許換え(法人成り)する方法
宅建免許は業として個人と法人いずれにおいても取得が可能です。
新規宅建免許取得の段階で、個人で免許を取るのが良いか、法人が良いかとご相談を頂くことが多いですが、個人で取った場合でも将来的に法人へ移行する予定がある場合は、最初から法人で免許を取得した方が良い場合がございます。
個人で宅建業を始める場合は、会社設立などの手間やコストを省くことができるため、代表者が宅建士の資格を持っていれば比較的容易に業としての免許取得が可能となります。
申請費用や協会費用については、個人でも法人でも変わりません。
個人で免許を取得した後、事業が軌道に乗るなどして法人化(法人成り)を検討することとなった場合、単純に会社を設立するだけでは足りません。
宅建免許については、個人から法人に引き継ぐことができないため、法人として再度新規の申請が必要となります。当然免許番号も変わるため、業者票の修正等が必要になります。
但し、都知事免許については、個人から法人として新規申請する際に
- 本店所在地
- 代表者
- 専任取引士
に変更がなければ法人成り申請として扱い、法人としての申請中でも個人免許に基づいて営業を続けることができます。
上記3点を変更して法人申請する場合は、完全新規扱いとなり免許申請中は営業ができなくってしまうため注意が必要です。
法人成り申請の申請方法についても注意が必要です。
申請書については法人として新規の申請書を作成する必要がございます。変更届ではありません。
申請書に添付する事務所写真については、個人としての業者票の掲示が必要で、入口とポストには登録した個人の屋号と法人名の併記が必要です。
法人としての宅建免許が下りた後、個人事業の免許は使用しないことの誓約書の添付と個人免許廃業の届出も必要です。
また、保証協会については以下の書類の提出と追加費用が発生します。
全宅(ハト)
事務所調査を再度行うかどうかは支部に寄ります
提出物
① 変更届
② 連帯保証書・誓約書
③ 会員権承継申請書
④ その他支部で必要とされるもの
負担する金額
① 弁済業務分担金(600,000円)は新たに積み直し
② 事務手数料 業協会¥10,000、保証協会¥40,000
③ その他保証協会については年会費の月割計算 ¥500×年度末までの月数
保証協会の会費については、供託日が年度最終の3月26日を超えると、個人業者の分が引き落とされてしまうので注意
全日(ウサギ)
事務所調査無し
提出物 新規と同様の書類
負担する金額
① 弁済業務分担金(600,000円)は新たに積み直し
② 事務手数料はないが、官報掲載料として¥20,000程度が差し引かれた金額が7か月ごろに返却される
以上
このように法人成りする場合は、手間と費用がかかり、弁済業務分担金60万円を再度負担する必要がございます。個人として供託した分担金60万円は返金されるため、実質的には事務手数料等以外の負担は発生しませんが、返金は半年以上先になるため、一時的な負担は必要となります。
その他契約書式の修正や印鑑等の作成も必要となります。
とは言え、これらの負担と個人事業主として消費税の免税期間を経てから法人成りし、再度法人としての消費税免税を得るなどの節税対策を取ることで、上記以上のコストダウンを図ることを念頭に置いている方は、個人事業主からのスタートでも問題ありません。
費用よりも免許番号が変わり、(1)に戻ってしまうことをデメリットに感じる方もいらっしゃるので、個人か法人どちらで宅建免許を取得するか事前によく検討して頂く必要がございます。
当事務所に宅建免許申請をご依頼頂くメリット
宅建免許取得率100%!13年連続全国1位の申請実績がございます
当事務所に宅建免許申請のご依頼を頂いたお客様で免許が取得できなかったケースは1件もございません。
直近約10年間、全日本不動産協会より新規申請実績最多の行政書士事務所として毎年表彰されている実績がございます。
大臣免許から他府県免許換え、自己供託による免許取得、M&Aや上場会社の免許申請も対応可能です。
弁護士事務所や免許取得に自信のない同業者様からのご依頼も多数頂いております。
複雑な案件も喜んでお引き受けさせて頂きます。
これらの実績を評価されて出版社からのオファー(自費出版ではありません)により不動産開業書籍を執筆しております。
ご相談は無料
会社設立から宅建免許取得までのご相談はもちろん、免許取得後の各変更届出や免許換えなどのご相談も全て無料となります。
最短スケジュールのご案内
お問合せ頂いた段階でお客様のご要望を伺い、どこよりも早い免許取得のスケジュールをご案内致します。
これは各行政と保証協会と日頃からやり取りしている弊所だからご提案できるスケジュールとなります。
東京都の宅建免許申請において、他の事務所様から約○○日とスケジュール案内された方は弊所に一度お問合せ下さい。
具体的に○月○日から営業開始可能と明確に回答致します。
完全返金保証
当事務所に宅建免許申請のご依頼を頂き、免許が取得できなかった場合は、費用全額返金致します。
宅建免許申請窓口である東京都庁に近い事務所です
宅建免許申請は郵送やオンラインによる申請ができないため、必ず東京都庁の不動産業課の窓口に提出が必要となります。
弊所は都庁から近いため、イレギュラーな内容が発生した場合でもすぐに対応可能です。
事務所概要はこちら
事務所へのアクセス方法はこちら
株式会社や合同会社等の不動産会社設立から公的融資まで対応
当事務所は、宅建業者様の開業支援、開業後のフォロー等を専門としているため、免許取得前の会社設立から免許取得、さらには宅建業に関する融資の申請(資金調達)までを一括してお引き受けすることが可能です。
会社設立から免許取得までご依頼頂いた場合は、会社設立の書類を作ると同時に宅建免許申請書の作成も並行して行うため、会社の登記が完了したその日に免許申請を行い、さらには、同日に保証協会の入会申請まで行います。
このように全てを円滑に進めることで、無駄な時間を費やすことなくお客様に開業して頂くことが可能となります。
また、宅建業に関する公的融資の実績も豊富ですので、金融機関が納得する現実的かつ綿密な事業計画書を作成することが可能です。
弊所がお引き受けした案件において宅建免許が取得できなった案件は1件もございません!
賃貸借契約書や不動産売買契約書等、宅建業に必要な契約書式を無料配布
宅建業者は、重要事項の説明義務や書面交付義務などにより、多くの場面で契約書やその他の書類の準備が必要となります。しかし、これらの書式を全て事前に社内に備え付けるのは容易ではありません。
そこで、当事務所に宅建業免許申請のご依頼を頂いたお客様には、当事務所に備え付けている契約書や覚書、その他請求書や納品書など、2000通以上の書式を無料で提供致します。これで、社内書式の整備などの事務作業に時間を取られる必要が無く、人件費等のコスト削減にも繋がります。
「書式例」
不動産売買契約書、建物賃貸借契約書、借地権設定契約書、サブリース・マスターリース契約書、賃料増額通知書、営業委託契約書など、他約2000通
宅建業に精通した税理士・司法書士・弁護士などの専門家を無料で紹介
会社設立・宅建業免許取得後は、様々な税務・法務・労務の壁に経営者は悩まされます。そこで、宅建業に精通した各専門家をいつでも無料で紹介致します。宅建業に限らず、会社設立後は税理士が必要になることが多いのですが、宅建業(売買など)は登記関連の手続がありますので、司法書士の力が必ず必要になります。また、敷金返還に関するトラブルなどで弁護士の力が必要になることも多々あります。
そうした事態に備えて、当事務所ではお客様のご要望に応えられる専門家のネットワークを構築し、いつでもどこでも各専門家を紹介できる体制を構築しております。
ご紹介の後、その事務所へ業務のご依頼をされるかどうかはお客様の自由ですので、他の事務所へ業務をご依頼されても全く問題ありません。
法定講習の優先的受講
宅建士証の更新や登録の際の法定講習は1~2カ月先まで満席でなかなか受講できないというのが一般的です。
早く営業開始したいにも関わらず法定講習を受けないと新規申請ができないという方もいらっしゃるかと思います。
弊所のお客様につきましては、弊所から法定講習機関にお話することで満席の日程でも席を確保してくれる場合がございます。
通常の予定よりも1カ月早く受講出来る場合もございますので、法定講習の受講にお困りの方は是非ともお声がけ下さい。
※優先的受講の絶対的お約束は出来かねますので予めご了承下さい。お客様の状況により通常の受講となる場合もございます。
宅建免許更新期限を無料で管理
宅建免許の有効期限は5年です。5年後に更新手続きを怠りますと免許は自動的に失効しますので、更新期限が近づいて参りましたら弊所からお声がけ致します。
宅建免許に限らず、自社で保有されている他の許認可(建設業許可など)も仰って頂ければ弊所にてスケジュール管理致します。
弊所のお客様限定でいえらぶCLOUDやコピー機.comのお値引きがございます
当事務所のお客様限定でいえらぶCLOUDがウェブサイトやシステムの制作費や月々の保守代を大幅に値下げします。
弊所にご依頼頂く前でも、一度いえらぶの話を聞いてみたい、見積もりを取りたいという方は、先行してご紹介も可能ですので、まずは一度弊所にご連絡下さい。
コピー機.comにつきましても、不動産開業に必須の複合機や電話機を大幅値下げします。
相見積もりももちろんOKです。
宅建免許申請に必要な電話番号の手配から機器の納品まで最短スケジュールにて対応して頂きます。
こちらも弊所ご依頼前の先行紹介は可能です。
いずれも当事務所経由とお客様が直接ご依頼された場合とでは、導入スピードからコスト面まで大幅に差が出ます。
お客様にご満足頂けるよう弊所からも念押し致しますのでコスト削減のお役に立てることと思います。
新規開業時の売上確保(新規顧客の開拓)にウチコミ!を紹介します
1万人以上の大家さんが利用しているウチコミ!なら、新規参入でも大家さんと直接繋がれる為、新規開拓の労力や集客コストを押さえることが出来ます。
地域担当制により加盟枠に限りがありますが、弊所経由であれば優先的に対応していただけます。
詳細については、以下よりお問合せ下さい。
新規開業時の売上確保(新規顧客の開拓)にHousii(ハウシー)を紹介します
ポータルサイトを利用した顧客獲得は競争が年々激化しており、広告費が高まる一方です。競争が激化するということは広告の反響率も以前に比べると落ちているのが現実です。
ポータルサイトからの脱却、又はポータルサイトを併用して営業を行う手段としてHousiiは有用となります。待ちの営業ではなく、攻めの営業ができるツールとなります。
弊所のお客様ご依頼特典をご用意頂きましたので、興味のある方は下記サイトをご確認の上、直接お問合せしてみて下さい。
代表行政書士山下の執筆書籍ご購入者様にはお値引き致します
当事務所代表行政書士の執筆書籍「不動産屋を開業して絶対儲かる74のヒケツ」ご購入者様につきましては、弊所報酬につき通常料金から書籍代をお値引き致します。
お客様との信頼関係構築を第一に考え、
迅速かつ丁寧なサービス提供をお約束致します。
関東一円対応!相談問い合わせ無料
にお悩みの方は
遠慮無くお問い合わせ下さい!